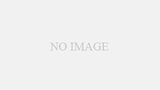食養を知り、まず始めたのが土鍋のご飯炊き。その次は朝晩の梅醤番茶を飲むことでしょうか。
若杉ばあちゃんの本を読んだらきっと実践してみたくなると思います。
朝だるいな~とか、体の調子が良くなかったり、風邪気味だったり、貧血、冷え性、食べすぎた時だって、これを飲めば体の調子が良くなってきます。
本で勉強していた時は、梅醤番茶もたくさん飲めばいいのだと勘違いしてたっぷりお湯呑みに作り飲んでいました。オンラインのマスター講座を受講してからはきちんと適量、適塩で飲むこと、たくさんの三年番茶ではなく、50㏄くらいでいいということを学び、きちんと飲み続けることができています。
濃ければいいとかしょっぱければいいわけではなく、自分の体が求めている濃さで美味しくいただくことが大切です。
子供も調子が悪くなると熱湯で梅醤ピューレを割、冷まして飲ませています。風邪気味の時や咳がひどいとき、お腹が痛いと訴えてきたときはすぐ飲ませてきました。またごちそうを食べた後にも飲むようにしていたら、今度は自分から体調が悪いと梅醤番茶が飲みたいと言ってきます。
また、私が飲んでいると僕も飲むといってきます。こうして自分の体調をコントロールできるようになってくるのです。悪くなってしまう前に自分で対策をとることができるおかげで、ほとんど病気と病院には無縁になります。子供に梅醤番茶なんてと思うかもしれませんが、子供もおいし~いと言って飲みます。さすがに毎日は飲ませていませんよ。本人が飲みたいと言った時にあげています。体の調子がよくなるとわかれば自分から飲んでくれるので助かります。
以前実家の物置から祖母が残してくれた梅干しを発見。だいぶ前のもので梅酢がゼリー状になっていました。見つけたときは祖母に感謝し、ありがたく家族でいただきました。私が子供の頃、祖母が庭で梅干しを作るところを見ていました。まだ土用干しの段階の梅をつまみ食いしてその酸っぱさにびっくりしたのを覚えています。当時庭には梅の木がありましたし、裏山や近所の山にも梅の木を植えていました。赤しそも畑で育てていたのか勝手に生えていたのかありました。祖母は身近で育てている材料を使い丁寧に梅干しを毎年作っていました。子供のころはほとんど食べた記憶がないくらいですが、祖母は時々体調が悪いと梅干しをお茶にいれて飲んだりしていました。
三つ子の魂百までですね。私も食養に出会い、祖母が漬けていたように実家の梅の実を収穫し、毎年漬けています。梅の実が少ししか採れないときもいい梅を買い作り続けています。
梅干しは常温保存でき、日持ちする優れた保存食ですよね。少量でもいざという時のために毎年作っておくことが大切です。
作っておけばいざという時に大活躍します。梅干しを作る時に出来る梅酢も一緒に保存し、毎日の料理やお手当に使うことができます。
夏場はご飯が傷みやすいので梅干しを入れてご飯を炊いたり、梅酢を手に付けおにぎりを握ったりしてきました。日々給食で食べている砂糖の毒を消してくれますのでありがたいものです。
昔の知恵もどんどん活用していきたいですね。